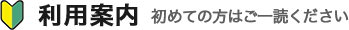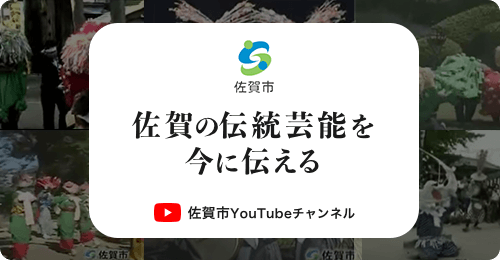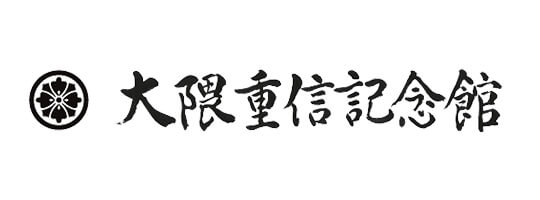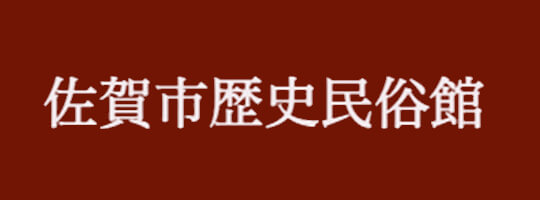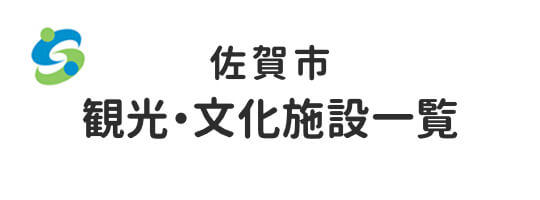ピックアップアーカイブ pickup
-

唐人町の由来
唐人町の起源は、天保13年(1842)7月、御用荒物屋・川崎勘四郎が佐嘉・鍋島藩に提出した、『御用唐人町荒物唐物屋職御由緒書』にみることができる。 それによると、勘四郎の先祖で高麗人、李宗歓(りそうかん)が、唐人町の始祖である。 李宗歓は、高麗は吉州、竹浦の川崎(現、朝鮮民主主義人民共和国、吉州ではないかと思われるが定かではない)に生まれたと記されており、当地ではかなり知られた武人かつ文人であり、相当の地位を得ていたようだ。 宗歓一族の墓は、唐人1丁目の浄土宗鏡円寺境内に現存する。
-
天満社 (舟津)
祭神 菅原道真 配祀 辨財天 創設年代 貞享元年(1684) 沿革 龍造寺隆信が勧請した島の内七天神社のうちの1社である。